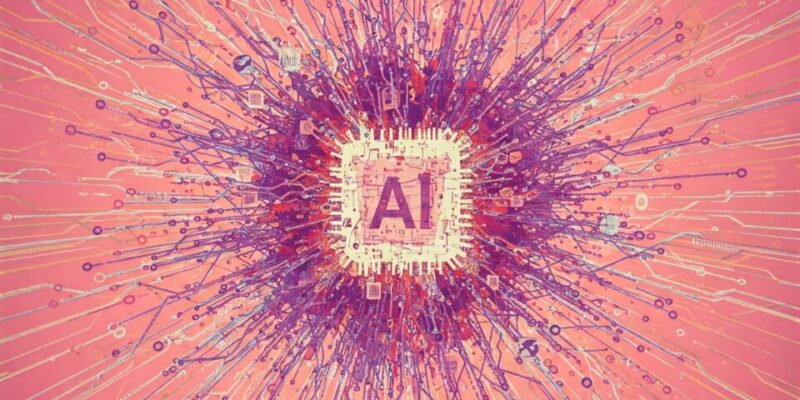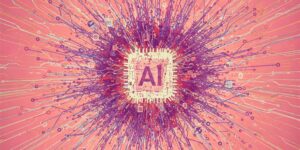生成AIとは、文章・画像・音楽などを自動で作り出すAI技術のこと。この記事では、代表的な生成AIの種類や、それぞれの特徴、メリット・デメリットを初心者向けにわかりやすく解説します。さらに、活用方法や実際に使う際の注意点についても詳しくご紹介します。
わたし自身がAIを活用しながら学んだことや、初心者でもすぐに試せるAIの使い方をシェアしていきます。「一緒に試してみよう!」という共学びスタンスで、楽しく学んでいきましょう!
1. 生成AIとは?
生成AIは、人間が行う創作活動をAIが自動で行う技術です。最近では、さまざまな分野で利用が進んでいます。具体的には、次のようなものがあります。
- 文章生成AI:指定したテーマやキーワードに基づいて文章を作成します。例えば、「旅行に関するブログ記事を書いて」と依頼すると、旅行に関する自然な文章が自動で作成されます。
- 画像生成AI:テキストで「青空の下に咲くひまわりの絵を描いて」と入力すれば、そのイメージに基づいた画像を生成してくれます。デザインのアイデア出しにも役立ちます。
- 音楽生成AI:作りたい雰囲気を指定することで、自動的にオリジナルの音楽を作成します。例えば「リラックスできるBGM」と指示すれば、それに合った楽曲を生成します。
- 動画生成AI:ナレーション付きの動画を自動で作成してくれるツールです。例えば、商品の説明動画を簡単に作成することが可能です。
これらの生成AIは、クリエイティブな作業を効率化し、新しいアイデアの創出をサポートしてくれます。初心者でも使いやすいツールが多く、活用すれば日常の作業がよりスムーズになるでしょう。
2. 代表的な生成AIの種類と特徴

2-1. 文章生成AI
- 特徴:与えられたキーワードやテーマに基づき、自然な文章を作成。
- 代表例:ChatGPT、Bard、Claude
- 時間短縮:ブログ記事や資料作成がスピーディに。
- 多様な文章が作れる:多彩な表現が可能。
- 誤字脱字の少ない文章を自動生成。
- 内容の正確さに注意が必要。(生成AIが嘘をつくことがある)
- 長文になると、情報がブレることがある。
- ニッチな内容だと情報が不足する場合がある。
2-2. 画像生成AI
- 特徴:入力したテキストからオリジナルの画像を生成。
- 代表例:DALL-E、Midjourney、Stable Diffusion
- 独自のビジュアルコンテンツを簡単に作成。
- アイデアの可視化がしやすい。
- デザイン案のイメージ作りにも便利。
- 複雑な指定が難しい場合がある。
- 著作権に注意が必要。
- リアルな画像は不自然に仕上がることも。
2-3. 音楽生成AI
- 特徴:メロディーや伴奏などの音楽を自動で作成。
- 代表例:AIVA、Amper Music、Soundraw
- 簡単にオリジナル楽曲を作れる。
- クリエイティブなアイデアの幅が広がる。
- 商用利用可能な楽曲が手軽に作れる。
- 人間の感性には及ばない場合がある。
- 独自性に欠けることも。
- 細かい音楽のニュアンスが出にくい。
2-4. 動画生成AI
- 特徴:簡単な設定で動画コンテンツを作成。
- 代表例:Synthesia、Pictory、Runway ML
- 動画制作の時間とコストを大幅削減。
- テキストからナレーション入りの動画が作れる。
- 商品紹介やプレゼン資料に最適。
- 演出や細かな編集には限界がある。
- 見栄えに制限がある場合も。
- 人間の自然な表現が難しいことがある。
3. 主要な生成AIツールの比較
3-1. ChatGPT
- 特徴:OpenAIが開発した対話型AI。多様な言語に対応し、柔軟な文章生成が可能。
- 得意分野:会話、記事作成、コードの生成など。
- 良い点:直感的に使えるインターフェース、学習データが豊富。
- 注意点:情報の正確性には注意が必要。

3-2. Claude
- 特徴:Anthropicが開発したAIで、安全性と倫理を重視した設計。
- 得意分野:ビジネス向けの文章作成や資料作成。
- 良い点:リスクの少ない出力、慎重な情報提示。
- 注意点:自由度が少し制限されることがある。

3-3. Gemini
- 特徴:Googleが開発した次世代AIモデルで、言語と画像処理に強み。
- 得意分野:データ分析、情報検索、コンテンツ生成。
- 良い点:最新の情報に強く、Googleのサービスと連携しやすい。
- 注意点:情報の鮮度に依存する場合がある。


3-4. Google Studio
- 特徴:GoogleのAI開発ツールで、データ可視化やダッシュボード作成に強い。
- 得意分野:ビジュアルデータ分析、マーケティング資料作成。
- 良い点:視覚的にわかりやすく、プレゼン資料に最適。
- 注意点:高度な設定には専門知識が必要。
4. 生成AIの活用法
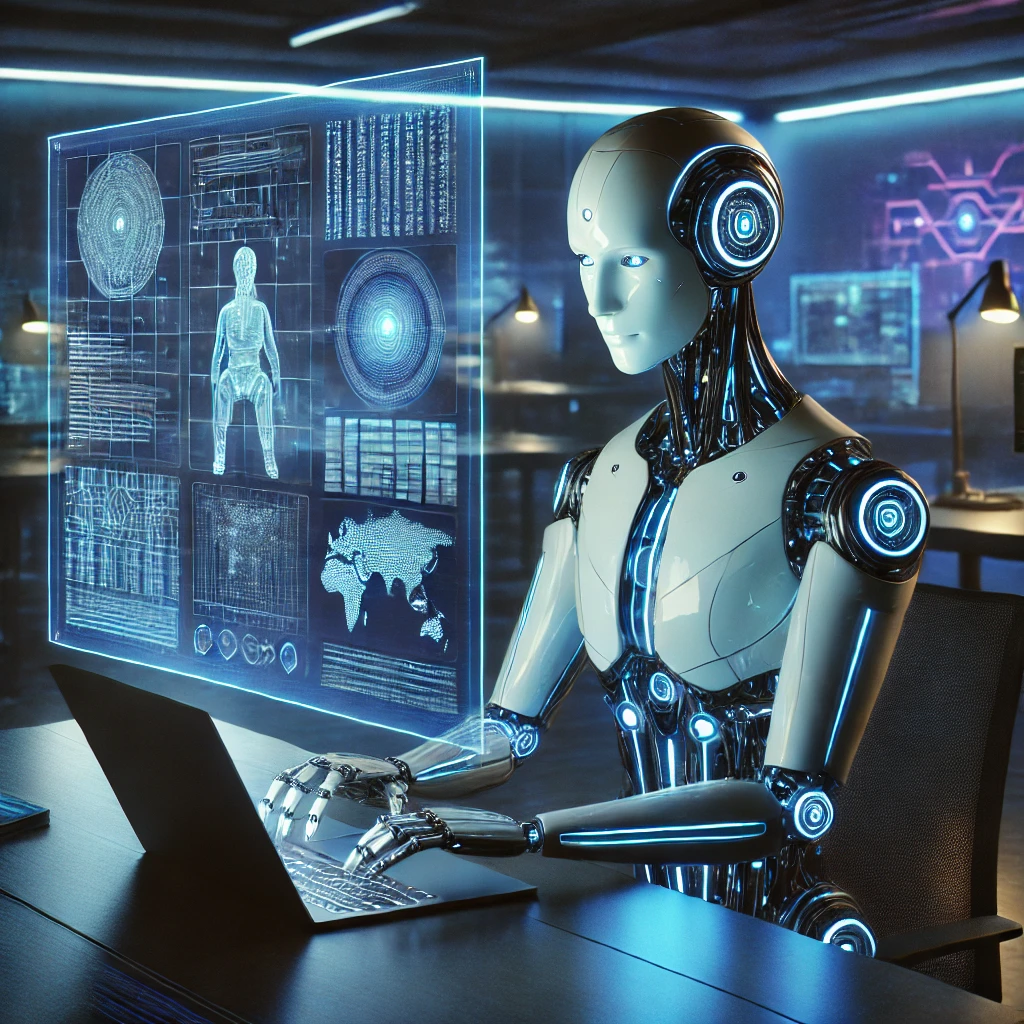
- キーワードを入力するだけで、簡単に記事や投稿文を作成。
- 画像生成AIでアイキャッチ画像を制作。
- 動画生成AIで簡単な紹介動画を作成。
- 提案書や企画書の作成を時短。
- 広告用の画像やキャッチコピー作成。
- プレゼン用の動画制作に活用。
- オリジナル音楽を作成し、配信や販売。
- イラストを作りSNSで発信。
- ブログ記事の執筆を効率化。
5. 生成AIを活用する際の注意点
生成AIを上手に活用するには、下記のようなことに注意する必要があります。
生成AIを活用する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを意識することで、より効果的にAIを活用でき、トラブルを防ぐことができます。
「生成AIが嘘をつく(🚨ハルシネーション1)」ことがあると言われますが、それは生成AIが情報収集し、不足分を勝手に補ったり、推測したりすることがあり、事実と異なる回答をすることがあるからです。
5-1. 著作権と知的財産権
- 生成AIが作成したコンテンツでも、著作権の取り扱いには注意が必要です。
- 既存の作品に類似したデザインや文章が生成される可能性があります。
- 商用利用を考えている場合は、利用規約をしっかり確認しましょう。
5-2. 情報の正確性と信頼性
- 生成AIは学習データに基づいて情報を提供するため、誤情報が含まれる場合があります。
- 特に専門的な分野や最新の情報は、自分でも調査して確認することが重要です。
- AIが生成した内容をそのまま使用せず、必ず内容の検証を行いましょう。
5-3. プライバシーと個人情報の取り扱い
- AIに個人情報を入力する際は、情報漏洩のリスクを意識する必要があります。
- 機密性の高いデータは、AIに入力しないことが推奨されます。
- 使用するAIツールのプライバシーポリシーも確認しておくと安心です。
5-4. 倫理的な配慮
- AIが生成するコンテンツが差別的、攻撃的、または不適切な内容にならないよう配慮が必要です。
- AIが出力した内容が社会的に問題がないか、倫理的に問題がないかを常に意識して利用しましょう。
5-5. AIの限界を理解する
- 生成AIは万能ではなく、特にクリエイティブな要素や独自性には限界があります。
- AIに頼りすぎず、人間の感性や直感も取り入れて、より良いコンテンツ作りを心がけましょう。
6. まとめ
生成AIは、文章・画像・音楽・動画と幅広い分野で活用されています。初心者でも簡単に利用でき、作業の効率化やアイデアの幅を広げることができます。ただし、正確性や著作権には注意が必要です。
まずは実際にAIを使ってみて、どのような成果物が作れるのかを体験してみましょう。生成AIの可能性は無限大!自分に合った使い方を見つけて、創作の幅を広げていきましょう!
続きは、また明日! 一緒に頑張りましょう!
- ハルシネーションとは・・・
🚨事実と異なる情報を生成する現象: AIが、学習データに存在しない、または誤った情報を、あたかも事実であるかのように生成してしまうことです。
🚨嘘をついているわけではない: 人間が意図的に嘘をつくのとは異なり、AIは学習したパターンに基づいて最もらしい情報を生成しようとした結果、誤った情報が出てきてしまうと考えられています。
🚨原因は様々: 学習データの偏り、データの不足、AIモデルの限界などが原因として挙げられます。 ↩︎