生成AIの時代にブログはオワコンになるんじゃない?という話しを耳にしました。わたしは、疑問視していますけど。
その話の元は、ChatGPTなどの生成AIの台頭により、誰もがブログを短時間で書けるようになったから、大量生産できるブログが価値を下げたから、などいろいろ言われていますね。
一方で、「AIに仕事を奪われるのでは?」「自分の文章に価値はあるのか?」と不安を感じているブロガーもいらっしゃるのでは?
本記事では、そんな生成AI時代において“埋もれないブログ”を実現するため、おすすめしたい『人間×AI のハイブリッドブロガー戦略』を詳しく解説します。
生成AI時代の強いブロガーになりたくて、読者の心に響く、あなただけの価値あるコンテンツ作りができるようになるための記事です。
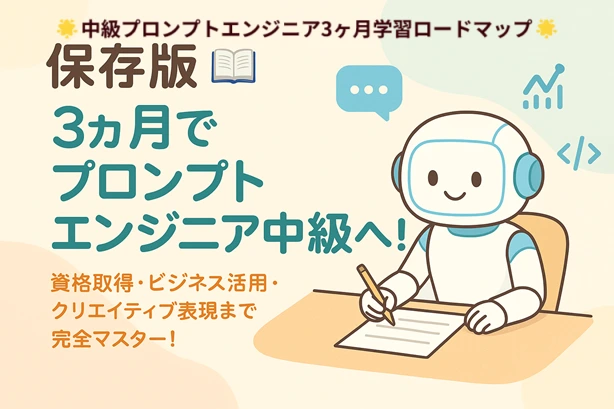
この記事は、📚 プロンプトエンジニア3ヶ月学習ロードマップ(中級編)の【第1ヶ月:中級編(基礎力アップ)】26日目です。
なぜ「ChatGPTでブログは終わる」と言われるのか?
ChatGPT(生成AI)は、膨大な情報を、瞬時に収集して記事を大量生成できるため、初心者でも簡単にブログ執筆が可能になり、ブログ投稿のハードルは劇的に下がりました。
それゆえ、以下の問題が発生しています。
読者にも検索エンジンにも響かない「AIくさい」記事が急増
SEO評価軸のE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)でも、AIコンテンツのみでは評価されにくくなっています。
※E-E-A-T:Googleがウェブサイトの品質評価を判断する、経験、専門性、権威性、信頼性の4つの要素のこと。その頭文字。
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| コンテンツの過剰供給 | 生成AIにより、類似の内容のブログが乱立 |
| SEOの厳格化(AEO,GEO対策にも) | 「誰が書いたか」、「誰の実体験か」を重視 |
| 読者離れ | テンプレート的な文体では共感が生まれにくい |

「生成AIくささ」の特徴
ではどんなところに、「生成AIくささ」は匂うのでしょうか?
私も実際にブログで見かける“ありがちな例”を挙げて、その特徴と問題点を紹介しますね。
特徴1:抽象的で薄い表現が目につく
🔻 例:「成功するには努力が大切です。ブログは継続が重要であり、常に情報収集を行いましょう。」
🧠 問題点
- どのジャンルやシーンにも使える“リサイクル感”が強く、具体性がゼロ。
- 経験に基づく背景やエピソードがないから、E-E-A-Tの「Experience 経験」が弱い。
- 検索ユーザーの「本当の悩み」には答えておらず、AEOでも不利。
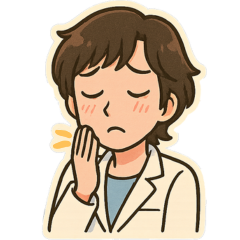 Sayoco
Sayoco「ンなことはわかってる!それで?」と言われそうなフレーズが並んでますね💦
特徴2:似た構文の繰り返しでマンネリ化
🔻 例:「まずは準備をしましょう。準備を整えたら行動します。行動した後は振り返りましょう。」
🧠 問題点:
- 構文の反復が目立ち、まるでテンプレみたいな文章。
- リズムや感情がなく、読者が読み進めたくならない。
- GEOのような生成AI検索では「類似パターン」の繰り返しとしてスルーされる可能性が高い。



ブログを他と差別化するために、わざとよく使うフレーズや、言い回しなどのケースは、これには当たりません。
特徴3:主語がなく、“誰の”体験かわからない
🔻 例:「このような方法でうまくいくケースが多いとされています。」
🧠 問題点
- 「誰が?」「どんな体験をした?」が書かれておらず、オリジナル性が欠如。
- AIで量産された記事に多い形式で、信頼性の欠如としてSEO評価が低下。
◆ 主語が自分↔️主語が誰かの違いの例 ◆
・ されています
・ かもしれません
・ 思われます
・ 考えられています…etc
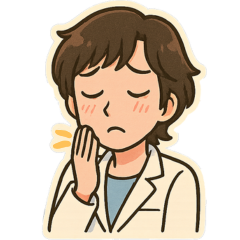
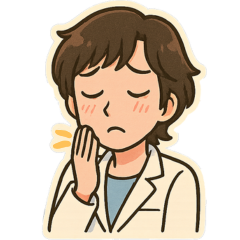
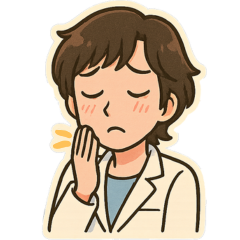
間違えないで欲しいのは、使わないことをすすめているのではなく”体験を語る場合は主語が自分でないとおかしいよ”という話し。
私の場合は、「誰に」「何を」「どう伝えるか」について考え、読者の心に届くように“生成AI×人間らしさ”のハイブリッド文章を作るように心がけてます。
AIくささを脱却するポイントとは
| NG特徴 | 改善のヒント |
| 抽象的で汎用的な表現 | 実体験や具体例を盛り込む |
| 同じ構文の反復 | 感情や比喩、ストーリーで変化をつける |
| 主語が曖昧 | 「私は〜」「読者は〜」で視点を明確に |
ブログがオワコンじゃない理由は?
その理由は、人間にしか出せない「人間くささという価値」があるからだと思います。
生成AIでは再現できない“人間味”が、今のコンテンツにも求められているのではないでしょうか。
生成AIにとって代わらない仕事、業務のポイントは、人間にしか出せない価値の存在。
ブログの場合求められているのは、生成AIでは再現できない“人間らしいコンテンツ”。
AEOやGEO対策の観点でも、人間の感情や一次情報、独自性が重要視されています。
人間だからこそ提供できる4つの価値
- 体験:自身の成功や失敗に基づく具体的なエピソード
- 感情:作者の葛藤・喜び・驚きなどの心の機微
- 洞察:情報に対する、作者の独自解釈や視点
- 信頼性:経歴や背景に裏付けられた内容であること
これらは読者の“共感”と“納得”を生み、GEOにおける生成AI検索でも可視性を高められる要素ですよね。




ChatGPTとのハイブリッドな執筆
6つの実践ステップ
実践ステップ一覧のステップバイステップをおすすめします。
生成AIをサブとして活用しつつ人間味を加えることで、検索エンジンにも読者にも響く“温度感のある記事”ができあがります。
🛠 実践ステップ一覧
何のジャンルについて書くか決め、読者に響くテーマを探して決める。
私は、タタキとしてジャンルやテーマをChatGPT(生成AI)に相談し、アレンジを自身でします。
テーマに合わせたキーワード、ロングテールキーワード、共起語や目次構成は、ChatGPT(生成AI)で情報収集。トピックの整理と類似記事、競合記事の分析も依頼。
キーワードや目次構成を元に、自分の言葉、特に体験や感情を交えた文章で執筆。
できた記事は、必ず読みながら編集・修正をする。読者目線や感情表現、文末のバランスなどを補強。
自分の語り口や経験を反映した指示に修正したり、読みやすい箇条書きや表作成をChatGPT(生成AI)に依頼したり、重複チェックもする。
この流れを繰り返すことで、生成AI×人間のハイブリットブログ記事の完成です!
「自分の軸」と「AIの効率」という良いとこ取りを両立しましょう💡



生成AIの出力は、Web上の情報を収集して作成されたもの。そのため、あなたの意図とは関係なく、他の方の著作権を侵害してしまうことも…。
私は必ず、文章のコピペチェックと、生成画像の画像検索をして確認してから公開します。
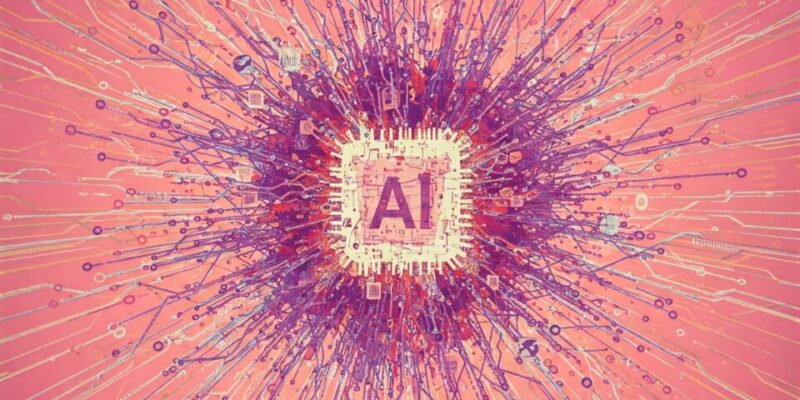
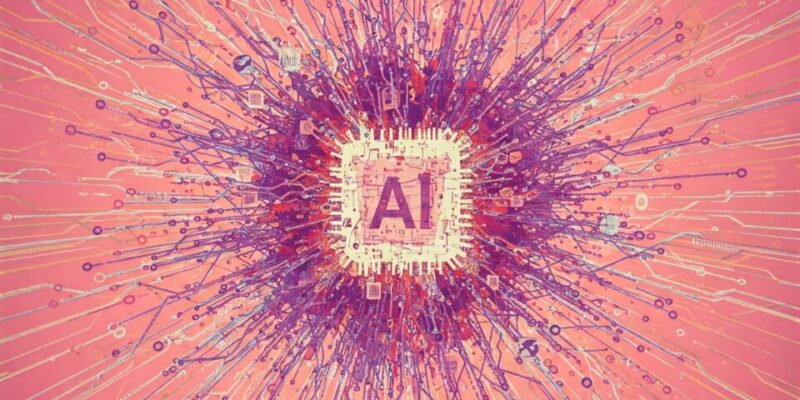
独自性のあるブログを作るための工夫
差別化をはかるためには、あえて自分の“経験則”や“視点”を見せることが有効です。
📌 差がつく3つの独自ブログのコツ
| タイプ | 特徴 | 効果 |
| ストーリー型 | 自身の経験談や背景に基づいたストーリー仕立ての記事 | 読者の共感を獲得しやすい |
| How I Think型 | どう考えて、どのようにしたか、思考過程や選択の理由を解説 | 読者の学びと信頼感をUPする |
| プロンプト公開型 | ChatGPTへの指示や改善経緯を共有・事例紹介 | AI活用層からの支持を獲得 |
AIに“再現できないもの”を敢えて見せることで、AEO/GEO対応の強いメディアに近づけます。
Q&A よくある質問
自分らしさを出す方法で、ペルソナを設定するなら『ChatGPTを仕事に活かす!初心者でもできるロールプレイ&ペルソナ活用術』の記事がおすすめです。
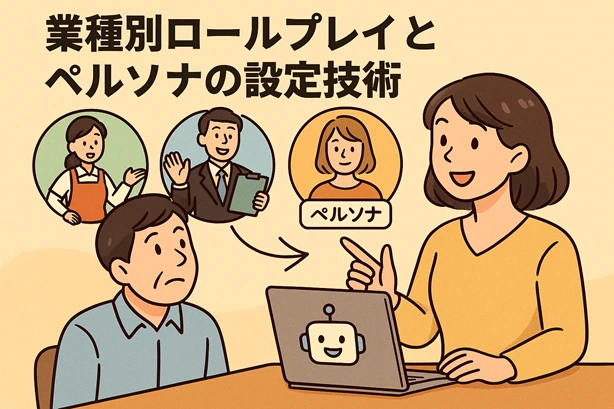
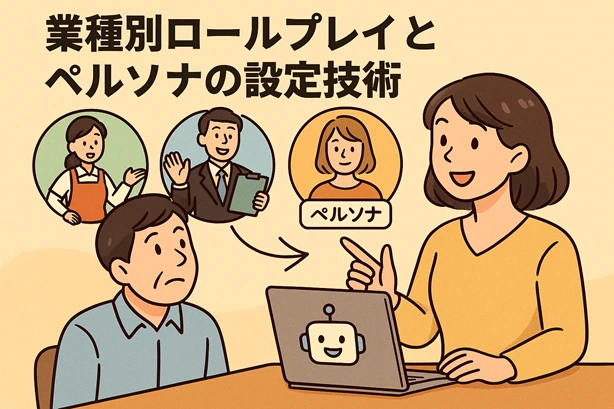
まとめ|ChatGPT時代に生き残る「選ばれるブロガー」へ
ChatGPT(生成AI)は脅威でも何でもないと私は感じています。
私にとって生成AIは、まさに共に戦う強力なパートナー!!
AIが文章を量産する時代だからこそ、あなたの視点・経験・肌感や温度が武器になるはず。
検索エンジンの最適化(SEO)、回答エンジン最適化(AEO)、生成エンジン最適化(GEO)のすべてにおいて、生成AI時代の到来は“人間らしさ”が今こそ評価される時代に。
まずは、自分にしか書けないことをプロンプトに落とし込み、「ハイブリッド記事」の制作に挑戦してみてください。
👉 今日から始めよう。あなたにしか書けない記事を、AIと共に。
次回予告
今回のテーマでは、生成AI時代のブログの未来についてでした。
そこであなたは、ChatGPTと人間が書く記事の質は、どのくらい違うか気になりませんか?
私は興味が湧いたので…
次回のテーマは、『ChatGPT vs 人間:ブログ記事の質を徹底比較!』をお送りする予定です。
お楽しみに🎵
生成AIのスキルアップは、独学で大丈夫ですか ? 独学では、応用力に不安がないですか?
スキルを磨くのは自分のため!学んで身につけたものは、あなただけの財産になると思います。
成長する達成感を味わえるのも、独学では難しいところ・・・💦。
こちらは押しつけがましくないので安心して参加できるセミナーです。
ちょっとでも興味があれば、無料参加をおすすめします!
簡単に手早く生成AIの何たるかを知ることができる、そんな無料オンラインセミナーがココ!
無料なのに速攻役立つ12大特典付き!👇👇👇




📢 ChatGPT(生成AI)を使うときの注意事項はこちら
🚨 AIでの生成物でも著作権に注意:文化庁AI利用者(業務利用者)のリスク低減方策(P25~)PDFで開きます。

